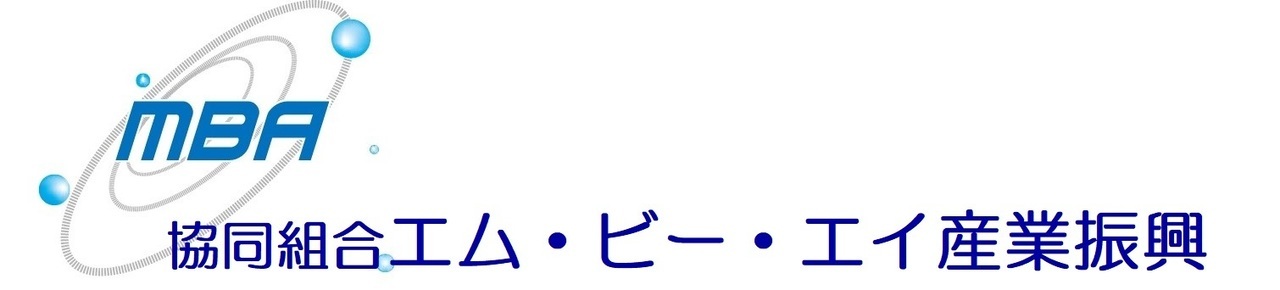理事長の感動日記 その6
毎日を人生最後の日だと思って生きてみなさい。
2011.8.29
24日に米アップル最高経営責任者(CEO)のスティーブ・ジョブズ氏が辞任しました。
アップルというと、それまでマイクロソフト社のウィンドウズの対抗馬でデザインに強いコンピューターという認識でしたが、2001年発売の携帯音楽プレーヤー「iPod」から一気に業績を伸ばし、「iPhone」、「iPad」の大ヒットに至っています。
2005年のスタンフォード大学卒業式でのスピーチで彼は、次のような言葉を卒業生に披露しました。
「来る日も来る日もこれが人生最後の日と思って生きるとしよう。そうすればいずれ必ず、間違いなくその通りになる日がくるだろう」。
このスピーチにある彼の人生は実に「不安定」です、今大成している人の人生ですが実に「不安定」です。そしてまた病に直面している現実も「不安定」です。
最近読んだ本に「自分を超える法」(ピーター・セージ著、ダイヤモンド社刊)があります。ちなみに著者は、世界No.1コーチであるアンソニー・ロビンズの史上最年少トレーナーと言われ自身も複数の事業を立ち上げ成功しています。
この本は意外な言葉で始まっています。
「人生の質は、居心地のよさを感じられる不安定の量に正比例する」
私が意外だと感じたのは、“居心地のよさ”と“不安定”という言葉が全く繋がらなかったのです。いかに自分の中に“安定”に固執した信念が出来上がっていたかということかもしれません。振り返れば脱サラして複数の事業に挑んだのは、自ら“不安定”を選択してきた証拠です。問題は選択した結果となる今、“居心地がよいか”ということではないでしょうか。そして、新たに生まれる“不安定”に対処することに居心地さを感じられるでしょうか。
おそらく多くの起業家にとってこの部分を線引きしないと矛盾からストレスを発し、的確な判断を逸する可能性が出てきます。
著者が言うように世の中に確実なものなど存在しませんが、自分の内なる部分は自分自身でコントロールできるはずです。この“不安定”を楽しむことができたらいいですね。
スティーブ・ジョブズ氏は、事業においては1985年に自らスカウトした人によってアップルを追放されましたが、96年に復帰しています。健康面では、2004年すい臓がんからの奇跡的な回復がありました。さらに2009年に肝臓移植手術を受けて復帰しています。
今回も十分に静養して復活してくることをお祈りしましょう。
最近読んだ興味深い本
2011.8.12
「われ日本海の橋とならん」加藤嘉一著 ダイヤドモンド社刊
最近読んで興味深かった本の紹介です。
著者は自他ともに認める今中国で最も有名な日本人です。北京在住の中国語が流暢なコラムニストで胡錦濤主席も彼のブログを読んでいるそうです。書名どおり一方に偏ることのない日中両国の考え方を学ぶ上で参考になります。
巻末では震災について触れ、当時中国で開催されていた全国人民代表大会が会期中だった時に、共産党幹部から届いたメールに「中国では全人会そっちのけで日本国民による地震・津波との戦いを詳細に報道しています。」とあったとか。
また、その後4月に北京大学で行われた世界的に有名な大学の学生たちが集まった会合で、「国家的な危機にあると内閣支持率が急上昇するものだが、どうして日本ではほとんど上がっていないのか」と指摘を受けたとか。
さらに、かなり鋭い指摘では、暴動や略奪もほとんどない日本人の冷静さや秩序を重んじる公共心の強さなどに対して、敬意をもって報じる中国報道に日本人として誇りを持つ一方、「冷静な日本人イコール『変化できない日本人』なのではないか」と。
そして日本の若者よ、海外に出ようと促し、その具体的な方法として、すべての大学生に2年間の猶予を与え、1年間老人介護施設で働いて、その資金で海外留学するのはどうかと提言したりしています。中国要人やメディアとの広い交友関係からくるホットな情報と、歯に衣着せぬ批評が興味深いです。
特に、「震災で時計の針は10年進んだ」という指摘は、経営コンサルタントの小宮一慶氏が「未来が早くやってくる」と言ったのと共通しています。皆様もご計画の前倒しをお勧めいたします。
最後に加藤氏は、「外交」と「教育」こそが今の日本にとって必要だと指摘していますが、私も全く同感です。当組合も技能実習生制度(人材)をとおして国際貢献すること、そしてNLPセミナーをとおして社員教育をはかること(さらには義務教育への導入も)をふたつの柱として活動しております。彼が言うように外と交わる中で人を育てることができれば、事業のパワーも倍増しそうです。
復興支援(メンタルケア)で石巻市を訪れて
2011.7.4
6月30日より2泊3日で、宮城県石巻市に復興支援・メンタルケア・コーチのボランティアに行ってきました。NLPコーチングのスキルを活用して、復興支援のコーチ3名と一緒に行ってきました。
初日に石巻専修大学に設けられた社会福祉協議会と災害復興支援協議会の方から現況をお聞きし、夜には支援協議会の日々のボランティア報告会にも参加しました。その際、たまたまおいでになった赤十字病院の看護師さんとも話す機会が与えられました。既に様々なボランティアが携ってきたようですが、震災後3か月を経過した今、さらに長期的なかかわりが必要なようです。
そして被災者だけでなく、今まで被災者を助けてきた対策本部のスタッフ、医療関係者及びボランティアの方々のコーチング、さらに今後新たに採用されるであろう支援員へのコーチングなどのニーズも感じました。
翌日、小学校に設けられた避難所と中学校に隣接する仮設住宅を訪れて、実際に被災者の方々の声をお聞きしました。6月より順次抽選により避難所から仮設住宅への移動が始まっています。早々に仮設住宅に当たって少し落ち着きを取り戻し将来設計についてコーチできる人もいれば、いまだ3.11で時間が止まっている避難所暮らしの方もいらっしゃいました。
避難所訪問での一つの気づきをシェアします。
震災後3か月が経過して、小学校の教室に一時は60人もの人が寝泊まりしていましたが、今は20名弱になりました。メンバーの構成は少し大きめの家族のように、おじいちゃんおばあちゃんがいて、若夫婦がいて、子供たちがいて・・・・・。今では本当に家族のようなのです。しばらく忘れていた昔の大所帯のようで、年寄りの身の回りのことを若者が手伝ったり、小さい子供の面倒を年寄りが見たりして温かい雰囲気が漂っています。
共有する大きな体験がそれを後押ししているのも確かです。このことが、一部の人たちにとって仮設住宅が当たっても避難所から出たがらない理由の一つになっています。
もう一つの大きな理由は、避難所では最低限ではありますが、生活していくための一切の物資が無料で提供されています。しかし仮設住宅では、食費や光熱費は自己負担となります。年金暮らしの年配の方々は取りあえず生活していけますが、育ち盛りの子供を抱えたご夫婦で仕事がない場合は深刻な問題です。
地域商店街の街づくり復興会議にも参加しました。
十数名のまさにこれから始まる立ち上げの集まりでした。事業主として会社が被災して大きな痛手を被っていますが、全員が個人的にも被災者です。発言のひとつひとつは生の被害データです。中小企業団体に所属している者として特にインパクトがありました。
全国からの支援の申し出はたくさんあるようですが、自分の会社の再建と街づくりそして一住民として、様々な立場から何を優先順位にして早急に手を付けていかなければならないか。たくさんの情報をいかに整理するかにおいてまずコーチを必要としているように感じました。
ある日突然、コツコツと築きあげてきたものが一瞬にしてすべて葬り去られました。そこへ多くの情報提供者が全く新しい街づくりへの様々な可能性を期待して近づいてきます。自分たちでやろうという気持ちと何でもかんでも援助してもらうのが当然と思う気持ちが混在しているようです。整理して、何がしたいのかを思いっきり自分に問いかけるためにコーチを必要としているようです。
石巻市を一望できる海岸に近い小高い山(日和山)に行きました。
前日に車で行った旧北上川の東側の石巻漁港周辺は上から見ても悲惨な状況です。そして両川岸には青いビニールで覆われた土豪が河口から上流に向かってずっと連なっています。今でも大潮になると川沿いの店舗には水が浸入してきます。地盤が70センチほど沈下したようです。しかしもっと驚いたのは南下にある川の西側の石巻港周辺です。壊滅状態です。
市の発表によると人口およそ16万2千人のうち死者3,100人、行方不明2,800人、数字をそのまま映像化したような光景でした。
NHKスペシャル「果てしなき苦闘」を見て
東京に向かう仙台の夜行バス待合室でテレビを見ていると、今回訪れた石巻市を特集していました。この数日間の裏付けをもらうかのように、初日にお会いしたあの赤十字病院が中心になっていました。
医療関係者の献身的な働きがありました。残念ながら私たちは医療行為によるお手伝いはできませんが、専門家も含む職種を超えた関係者へのコーチングの必要性を改めて感じました。それには、生半可な気持ちでは決してできないという真剣さが必要だと感じました。
そういえば、最初に訪れた避難所で洗濯しながら話を聞かせてくれたおばちゃんの言葉が忘れられません。10分ぐらいの会話の中で十数回繰り返していました。
「津波にあったら何も持つな。・・・・子供の手だけは離すな。」
このおばちゃんは被災から2日間を自宅の押入れの天袋の中で過ごしました。すごく寒かったのですが、ご主人の位牌だけは濡れないようにして、背丈まであった水が引き始めてから自力で脱出しました。
このことから何を学べるだろうか?私には何ができるだろうか?
「一人ひとりは違います。でも一人ひとりはつながっています。」
以上
突然!入国審査官がおいでになりました。
2011.6.7
入国審査官より電話がありました。
「MBAさんですね。今、技能実習生5名の講習をやっていますか?」
「はい」
「お宅のビルの前にいますがお伺いしてもよろしいですか?」
突然の訪問にびっくりしました。昨年の法改正後、申請どおりに講習が行われているかどうか、抜き打ちで各組合を訪問調査しているとのことでした。
当たり前のことをそのまま答えるだけの面談と、実際の講習風景・施設の写真撮影だけで、何らあわてることはないのですが、審査されることに緊張感がありました。
結果的に、「東京のど真ん中ですが、施設もコンパクトにまとまっていて、しっかり講習をやられていることがわかりました。」という評価をいただき、一安心しました。
当組合では、少人数の場合は組合事務所に併設している施設で、入国後一ヶ月の講習を行っています。訓練センターを使っての大人数の場合と比較してよい点は、実習生の気持ちがよく理解できるということです。一つ屋根の下で同じ釜の飯を食うと自然に心が通います。
昨晩も遅くまで残業をしていると、一時間ぐらい煮込んだ鶏の足の料理ができたから、一緒に食べないかと誘ってくれました。あのいわくつきの鶏です。
日曜日に210円で買ったというのです。どこで買ったのかと聞くと店の名前を言わないので、レシートを見せてと言うとないと言います。
???・・・・露店で買ったのです。新宿にそんなところをあったのか?
既に実習生の方が私より路地裏は詳しいのです。